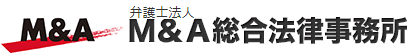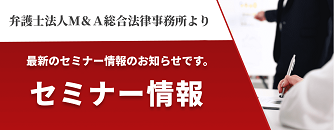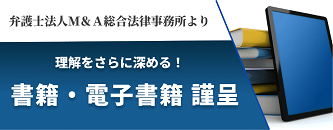会社の資金繰り(過剰債務・経営不振・債務超過・差押・連帯保証)に、お困りではありませんか??
破産・民事再生しなくても、会社分割(第二会社方式)を行うことにより会社を再建することが可能です。
会社分割による第二会社方式とは?
会社が債務超過に陥ったとして、そのままでは債務の削減(債権カット)ができない場合、会社を分割して、事業を新設会社に移し、旧会社に過剰債務を残して事業を過剰債務から切り離し、最終的には旧会社を破産又は特別清算させ、過剰債務を免除してもらうという方法です。
これにより、新設会社は、負債の少ない綺麗な会社に突然生まれ変わりますので、一気に企業再建が実現します。
銀行は、金融庁の関係や行内事情により、法的手続によらずに、私的整理で債権放棄に応じたり、債権の一部免除に応じることがなかなか困難ですので、このような「第二会社方式」を使って、直接的には債務の削減(債権カット)を行うことなく、実質的に債務の削減(債権カット)を実現する(否応なく回収できなくなったという形式をとる)のです。
詐害的会社分割という障害
なお、過剰債務に陥った中小企業が、銀行に対して事前に何ら通知、催告なく、突然、会社分割により新設会社を設立し、新設会社に事業を移してしまうケースもままありますが、そのような場合は、銀行から強硬な方法で抵抗を受けることが多くなっています。
銀行からの抵抗としては、債権者破産の申し立てなども行われますが、最近では、会社分割を詐害行為として取消すという「詐害的会社分割」との主張が一般的です。実際に、銀行の債権を一方的に削減しようとの相当乱暴な会社分割による第二会社方式が存在し、中小企業が「詐害的会社分割」であるとして裁判で敗訴している例が多くなっています。
そういう意味では、会社分割による第二会社方式も、銀行の承諾(あるいは黙認)の下で行うことが好ましいといえます。
この点、銀行としては、究極的には債務の削減(債権カット)につながり、自身の損失になる話ですので、銀行は積極的に承諾をしてくれることは多くないため、事実上黙認して頂けるならそれでよいと考える他ありませんし、銀行がその債権について償却(損金処理)が完了しているのであれば、あまりうるさく言われることもない傾向にあります。
会社分割による第二会社方式により企業再建を実現するためには
銀行についても、会社が破産したり民事再生を申立ててしまって債権の回収率が1-2%になってしまったりするよりも、多少長期間にわたったとしても、より多く回収したいという意向がありますし、そのような考え方は非常に経済合理的な考え方と思われます。そういう意味でも、銀行としても、会社が破産や民事再生になってしまうよりは、会社分割による第二会社方式でもよいので、それよりも多く債権を回収できた方が経済合理的なのです。ですので、銀行も会社分割による第二会社方式にやたらめったら反対するものではありません。
では経済合理的な会社分割による第二会社方式とはどのような企業再建方法でしょうか。
経済的合理性のある企業再建方法とは、法的整理(破産や民事再生)になった場合よりも銀行にとって多少なりとも有利な企業再建案ということです。すなわち法的整理(破産や民事再生)になった場合に回収できる債権の金額(一般的には多くても1-2%)以上の債権を、その会社が支払ってくれる企業再建方法の場合です。そのような、企業再建計画を作成したうえで、会社分割による第二会社方式を実行するのであれば、銀行は黙認してくれるでしょう。
会社分割により第二会社方式の手続き
中小企業再生支援協議会における企業再生スキームの多くは、この会社分割により第二会社方式です。
中小企業再生支援協議会が使用される理由は、中小企業再生支援協議会が経済合理的な企業再建計画となっているか確認してくれる(お墨付きを与えてくれる)ために過ぎませんので、勿論、中小企業再生支援協議会に申し立てたほうが好ましいですが、実務上は、必ずしも、中小企業再生支援協議会に申立を行わなくても、会社分割により第二会社方式は実現する傾向があります(なお、中小企業再生支援協議会は非常に小規模な組織ですのでマンパワーも少なく、困難な案件については回避し、申立を受理しない傾向にあります)。
そうであっても、やはり、経済合理的な企業再建計画を作成し、法的整理(破産や民事再生)になった場合よりも銀行にとって多少なりとも有利な企業再建案となっていることが重要となります。
会社分割自体は手続きとして特段難しい手続きではありませんのですぐに終了しますが、銀行一行一行との相対での交渉や銀行全行とのバンクミーティングによる交渉を経て、銀行に経済合理的な企業再建計画であることを理解頂きながら進めないと(あるいは黙認してもらって進めないと)、「詐害的会社分割」であるなどとの反論がなされ、手続きに障害が生じますので、専門の弁護士に相談しつつ手続きを進められることが好ましいと思われます。