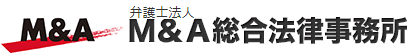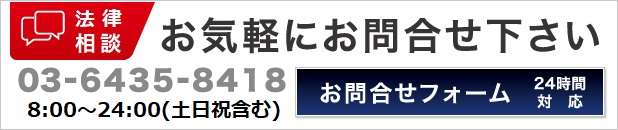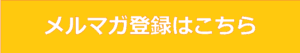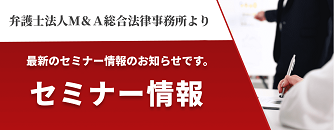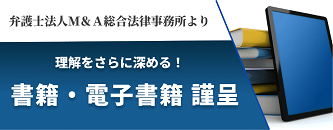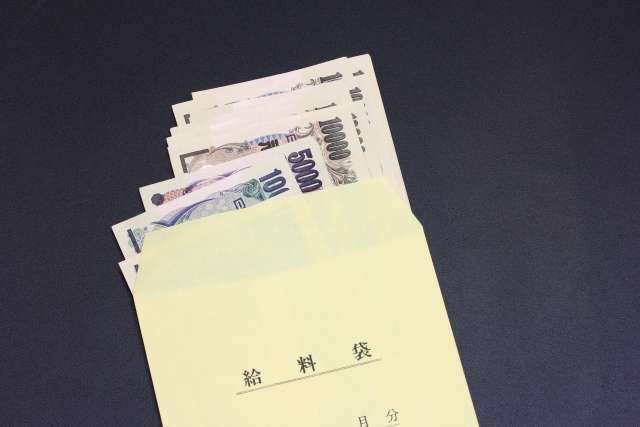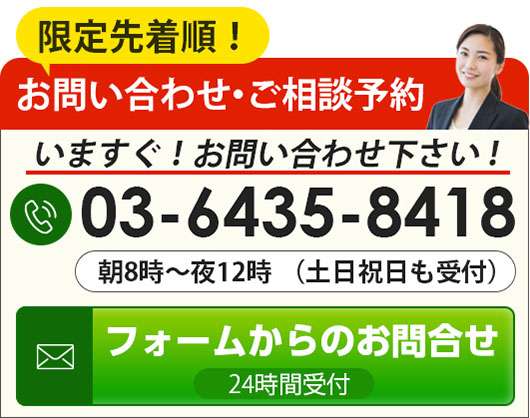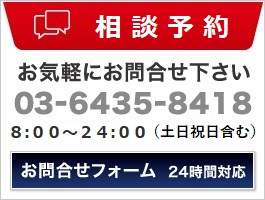会社の経営は、いつも順風満帆にいくとは限りません。業績や財務状況が悪化してしまい、立ち行かなくなる会社も非常に多いです。
そのような状況を放置しておくと、債権者への弁済、ゆくゆくは差押さえなどが行われ、最終的には事業の継続ができなくなる可能性が高くなります。
このようなリスクを回避するためにも、債務者は早めに企業再建に着手していかなくてはいけません。
しかし、中には「破産手続き・民事再生は避けたい」という方もいらっしゃるでしょう。
確かに、破産手続き・民事再生といった法的手段は手続きが複雑で時間がかかり、また債務が削減できたとしても、取引先の信頼関係が失われてしまい、取引の継続が難しくなってしまうなどのデメリットもあるためお気持ちはわかります。
そこでおすすめとなるのが、『私的整理』です。
『私的整理』ならば、対象債権者を限定できるなど柔軟に手続きができたり、手間や時間、費用を抑えられるなどといったメリットもあります。
ここでは、そんな『私的整理』とはどういったものか、その内容や私的整理ガイドライン、事業再生ADR、地域経済活性化支援機構、中小企業再生支援協議会の特徴などの情報を徹底解説していきます。
- 私的整理手続きとは?
- 会社が①債務の返済期限の延長(リスケジューリング)や②債務の削減(債務カット)が最もメリットがあるという状況とは?
- 私的整理ならば対象債権者を限定することができる
- 私的整理のメリット
- 私的整理の注意点
- 私的整理と法的整理の特徴の違いは?
- 私的整理ガイドラインを利用する
- 事業再生ADR、地域経済活性化支援機構、中小企業再生支援協議会を利用する
- 事業再生ADR、地域経済活性化支援機構、中小企業再生支援協議会の特徴
- 事業再生ADR、地域経済活性化支援機構、中小企業再生支援協議会の利用は強制ではない
- いずれにしろ法的整理や準則的私的整理手続きでも会社を手放さないといけない
- 弁護士が管理することにより私的整理が可能
- 必ずしも破産などする必要はない!!
- 早めに弁護士へ相談を行う
- まとめ
私的整理手続きとは?
 『私的整理』手続きとは、法的手続きによらずに相対での交渉により、①債務の返済期限の延長(リスケジューリング)又は②債務の削減(債務カット)し、企業再建を実現する手続きです。
『私的整理』手続きとは、法的手続きによらずに相対での交渉により、①債務の返済期限の延長(リスケジューリング)又は②債務の削減(債務カット)し、企業再建を実現する手続きです。
任意の手続きですので、決まった手続きというものはありませんが、銀行一行一行と相対で交渉をする場合と、全銀行を相手にまとめてバンクミーティングを開いて交渉をする方法があります。
銀行などの債権者としては、①債務の返済期限の延長(リスケジューリング)はともかく、②債務の削減(債務カット)をした場合、大きな損害が発生します。
銀行などの債権者としては、そのような損害が発生することは極力避けたいと思っており、①債務の返済期限の延長(リスケジューリング)や②債務の削減(債務カット)が最もメリットがあるという状況でないと、①債務の返済期限の延長(リスケジューリング)や②債務の削減(債務カット)に応じることはありません。
そこで、会社の経営状態が、本当に、①債務の返済期限の延長(リスケジューリング)や②債務の削減(債務カット)が最もメリットがあるという状況が最もメリットがあるという状況であるかどうかというのが重要になってくるのです。
この点、会社の経営者が、うちの会社は、①債務の返済期限の延長(リスケジューリング)や②債務の削減(債務カット)が最もメリットがあるという状況です、と言っても、銀行などの債権者としてはそれを信用するわけにはいきません。
そこで、この『私的整理』手続きでそのような①債務の返済期限の延長(リスケジューリング)や②債務の削減(債務カット)が最もメリットがあるという状況であるかどうかが判明するか、この『私的整理』手続きが、適正な『私的整理』になっているかが重要となってくるのです。
会社が①債務の返済期限の延長(リスケジューリング)や②債務の削減(債務カット)が最もメリットがあるという状況とは?
会社が①債務の返済期限の延長(リスケジューリング)や②債務の削減(債務カット)が最もメリットがあるという状況とは、どういう状況でしょうか。
すなわち、それは、①債務の返済期限の延長(リスケジューリング)や②債務の削減(債務カット)をしなければ、会社が倒産してしまう状況や、①債務の返済期限の延長(リスケジューリング)や②債務の削減(債務カット)をしなければ、これらをしなかった場合よりも債権の回収額が減少してしまう状況です。
例えば、①債務の返済期限の延長(リスケジューリング)や②債務の削減(債務カット)により、債務を半分に削減してあげれば、会社は存続でき、銀行などの債権者は、債権の半分を回収できたのにもかかわらず、それをしなかったため、会社が倒産してしまい、1円も回収できなくなったとしたら、それは、①債務の返済期限の延長(リスケジューリング)や②債務の削減(債務カット)が最もメリットがあるという状況なのです。
私的整理ならば対象債権者を限定することができる
また、法的手続きは、取引先を含め、すべての債権者を債権カットの対象として手続を進めなければいけません。返済案に従って、すべての債権者が有する債権のリスケジュールや債権カットを行うことができますが、その反面「事業価値の毀損が大きい」というデメリットもあります。
しかし、『私的整理』ならば対象債権者を限定できるため、事業価値の毀損をできるだけ抑えることができます。
たとえば、再建型私的整理ならば、取引先の債務はそのままにしておき、金融機関の債務だけを債権カットすることも可能です。
『私的整理』は、柔軟に事業再建を遂行していくことができるのです。
また、このように債権カットの対象を限定することにより、銀行などの債権者にとっては、①債務の返済期限の延長(リスケジューリング)や②債務の削減(債務カット)が最もメリットがあるという状況、すなわち、債権カットをしなかった場合(結果として破産する場合)よりも、債権カットをした場合の方が、債権の回収額が大きくなる、債権カットをすることにより債権の回収額が極大化するという、一件、矛盾した現実が実現するのです。
私的整理のメリット
費用を抑えることができる
『私的整理』は、法的整理のように裁判所が関与するというわけではなく、また決まった手続きがあるわけではありません。
ですので、法的整理と比較すると費用が廉価で済むケースが多いです。
柔軟な手続きが可能
前述の通り、対象債権者を限定できる『私的整理』は、柔軟な手続きを行うことが可能となっています。
また、法的整理のように手続きが法律により定まっているわけではない『私的整理』は、債権者との合意があればリスケジュールや債権カットなど、事業再建案を自由に決めることができます。
よって、法的整理と比較すると、短時間で手続きを完了できる可能性が高いのです。
企業や経営者の信用の毀損を抑えることができる
たとえば、破産をした場合、企業や経営者の信用は大きく毀損してしまう可能性が高いです。
しかし、『私的整理』に成功すれば、これまでの企業価値を維持しながら事業再建に臨むことができるようになります。
また、破産時と比較して債権者に対し多くの弁済を実施できるのも大きなメリットです。
私的整理の注意点
債権者全員の同意が必要
法的整理では、一定数の債権者の同意を得ることができれば手続きを行うことができます。
その反面、『私的整理』の場合は、協議を要請する債権者全員の同意を得ることができなければ手続きができないため、事業再建に臨むことができません。
一人でも債権のリスケジュールや債権カットに反対する債権者がいたら、『私的整理』は不可能となるのです。
なお、この点については、①債務の返済期限の延長(リスケジューリング)や②債務の削減(債務カット)が最もメリットがあるという状況、すなわち、債権カットをしなかった場合(結果として破産する場合)よりも、債権カットをした場合の方が、債権の回収額が大きくなる、債権カットをすることにより債権の回収額が極大化される状況であることを説明できれば、基本的に、皆さん同意していただけます。
なぜなら、①債務の返済期限の延長(リスケジューリング)や②債務の削減(債務カット)が最もメリットがあるという状況、すなわち、債権カットをしなかった場合(結果として破産する場合)よりも、債権カットをした場合の方が、債権の回収額が大きくなる状況だからです。
ですので、会社としては、しっかり事業計画を作成し、①債務の返済期限の延長(リスケジューリング)や②債務の削減(債務カット)が最もメリットがあるという状況、すなわち、債権カットをしなかった場合(結果として破産する場合)よりも、債権カットをした場合の方が、債権の回収額が大きくなる、債権カットをすることにより債権の回収額が極大化される状況であることを、銀行などの債権者に対して、しっかり説明することが重要なのです。
公平性(透明性)や強制力が欠けている
『私的整理』は、法的整理のように強制力があるわけではありません。
また、裁判所の関与がなく、非公開のテーブルで特定の債権者とのみ協議する『私的整理』は、一部の債権者が有利な条件になっている可能性もあり、その結果、どうしても公平性(透明性)が欠けてしまうのです。
『私的整理』は全ての債権者の同意を獲得しなければいけないため、公平性(透明性)についてどのようにして納得できる説明を債権者に対して行うかも重要なポイントとなります。
ですので、『私的整理』の場合は、弁護士が管理をして『私的整理』を主宰し、会社の財産調査をして、しっかり事業計画を作成し、①債務の返済期限の延長(リスケジューリング)や②債務の削減(債務カット)が最もメリットがあるという状況、すなわち、債権カットをしなかった場合(結果として破産する場合)よりも、債権カットをした場合の方が、債権の回収額が大きくなる、債権カットをすることにより債権の回収額が極大化される状況であることを、銀行などの債権者に対して、しっかり説明できなければいけないのです。
私的整理と法的整理の特徴の違いは?
『私的整理』と法的整理は、異なる特徴を持っています。
まず、『私的整理』は法的整理のように公平性(透明性)が高くありません。その一方法的整理は、裁判所が手続を進めるので公平性(透明性)を確保することができます。
ただし、裁判所を介すため、法的整理は手間や費用が重くかかってくる可能性が高く、それと比べると、『私的整理』は比較的負担が少なくなるケースが多いです。
債権者の同意に関しましては、『私的整理』を行う場合、債権のリスケジュールや債権カットのためには、協議の相手方となる債権者全員の同意が求められます。
しかし、法的整理ならば、一部の債権者の反対があったとしても返済案に従ってリスケジュールや債権カットを行うことができるので、債権者の同意という面では、法的整理の方が負担が少ないといえます。
しかし、これらは法制度がそうなっているということを説明しているのみであり、前述のとおり、債権カットをしなかった場合(結果として破産する場合)よりも、債権カットをした場合の方が、債権の回収額が大きくなる、債権カットをすることにより債権の回収額が極大化される状況であることを、銀行などの債権者に対して、しっかり説明できれば、『私的整理』により、債権カットが可能となるのであり、銀行などの債権者の同意も得られるのであり、法的整理を選択せざるを得ない場合というのは、よほどの場合しか存在しないものと思われます。
私的整理ガイドラインを利用する
『私的整理』は、どうしても公平性(透明性)に欠けてしまうため、そこで、「私的整理ガイドライン」に沿って整理手続きを行う手段もあります。
私的整理ガイドラインとは、公平で透明性のある『私的整理』を行うためのルールであり、法的拘束力こそないものの、金融機関などの主要債権者や債務者、ならびにその他の利害関係人によって自発的に尊重され遵守されることが期待されています。
事業再生ADR、地域経済活性化支援機構、中小企業再生支援協議会を利用する
 『事業再生ADR』や『地域経済活性化支援機構』『中小企業再生支援協議会』など、公平中立な第三者機関による制度を利用して私的整理手続きをする手段もあります。
『事業再生ADR』や『地域経済活性化支援機構』『中小企業再生支援協議会』など、公平中立な第三者機関による制度を利用して私的整理手続きをする手段もあります。
準則的私的整理手続きを言われ、私的整理と法的整理の中間的な制度です。
これらは、経済産業大臣などに認可された信頼できる機関です。
これらの機関を介すことで、より公正で透明性の高い私的整理を目指し、円滑に企業再建を進めることが可能となります。
ただし、どの機関も、手続きが大まかに民事再生や会社更生などの法的手続きと似ていますが、いずれも裁判所ではありませんので、柔軟ではあるものの、独自の手続きが必要となってきます。
事業再生ADR、地域経済活性化支援機構、中小企業再生支援協議会の特徴
事業再生ADR
『事業再生ADR』とは、産業活力再生特別措置法(産活法)に基づき、経済産業大臣の認定を得た特定認証紛争解決事業者(ADR事業者)が、その事業として行う私的団体です。
「ADR」とは、裁判外紛争手続きのことであり、法的整理と比較して柔軟な対応を取ることができます。
また、事業再生ADRによる私的整理手続きを行えば、終了するまでの間に発生する債務者の会社の事業の継続に必要となる資金を、「独立行政法人中小企業基盤整備機構」が債務保証してくれるため、いつでも借入を行うことが可能です。
その他にも、公平中立な第三機関が私的整理手続きを行う制度として、「地域経済活性化支援機構」もあります。
ただし、これらはいずれもJALやウィルコムといったような大企業を対象としています。
中小企業再生支援協議会
『中小企業再生支援協議会』は、「産業活力の再生及び産業活動の確信に関する特別措置法(産活法)」に基づき、公的金融機関や地域の金融機関、商工会議所や商工会連合会、中小企業支援センターおよび自治体などから構成された機関です。
また、中小企業再生支援協議会は中小企業庁の監督を受けた公的機関であり、中小企業は勿論のこと、医療法人、社会福祉法人、学校法人などの特別法人も対象とし、債権者と債務者の利害調整を行っています。
中小企業再生支援協議会による私的整理手続きは、公的な機関に申立を行い、公的な機関と一緒に、公的な機関の監督の下、再生計画案を策定していきます。
また、公的な機関の監督の下作成した再生計画であり、適正な私的整理手続きによる、適正な要件を満たしている私的整理の内容となりますので、「私的整理ガイドライン」の要件を満たしているものとなります。
その結果、公平性(透明性)が高いものとなるため、銀行などの債権カットを受け入れている債権者からしても、再生計画案を受け入れやすくなるのです。
中小企業支援協議会の手続きは非公開で行われる、銀行などの金融機関の債務のみを対象とした手続きです。
そのため、「取引先や従業員などに知られることなく会社の再建を果たすことができる」というメリットもあります。
経営保証など経営者の債務も一体処理
中小企業支援再生協議会は、経営者保証ガイドラインの制定に伴い、「保証債務整理支援業務」も行うようになっています。
これは、会社の①債務の返済期限の延長(リスケジューリング)や②債務の削減(債務カット)の手続きと並行して(又はそれとは別に単独で)、経営者保証ガイドラインに基づき経営者個人の保証債務について、①債務の返済期限の延長(リスケジューリング)や②債務の削減(債務カット)を行う手続きです。
これにより中小企業は、中小企業支援再生協議会に申し立てることにより、会社と経営者が一体として再建を目指して手続きを行うことができます。
勿論、保証債務整理支援業務は経営者保証ガイドラインに基づいて行われるものですので、経営者の自宅は華美な自宅でない限り喪失することはないということとなります。
事業再生ADR、地域経済活性化支援機構、中小企業再生支援協議会の利用は強制ではない
事業再生ADRや地域経済活性化支援機構、中小企業再生支援協議会にはそれぞれメリットがありますが、かといって必ずしも利用する必要があるわけではありません。
というのも、事業再生ADRや地域経済活性化支援機構、中小企業再生支援協議会はいずれも人員不足で、中小企業の債権まで手が回らないことが通常であり、また公的機関でもあるため、申立を受理してもらうためには厳しい要件と多額の費用(事前に会社精査の費用支出)が必要となるのです。
いずれにしても、対象会社が破産や民事再生を行った場合よりも、『私的整理』を行った場合の方が銀行やその他の金融機関の回収率が高くなりさえするならば、適正な『私的整理』として銀行やその他の金融機関は『私的整理』に協調することとなります。
すなわち、法的手続きのみならず、事業再生ADRや地域経済活性化支援機構、中小企業再生支援協議会などを利用した『私的整理』のいずれを採用することが最善であるかについて、これらの諸般の事情を考慮して、検討することが重要となります。
いずれにしろ法的整理や準則的私的整理手続きでも会社を手放さないといけない
ただ、非常に重要なポイントがあります。
いずれにしろ法的整理や準則的私的整理手続きでは、基本的に経営者は会社に残ることはできないのです。会社を手放さないといけないのです。
会社を経営破綻させた張本人である会社の経営者が会社に残るということは、同じ人が経営する以上、またその会社を経営破綻させかねないということで、銀行などの債権者にとっては、容認できることではないのです。
すなわち、①債務の返済期限の延長(リスケジューリング)や②債務の削減(債務カット)をしたとしても、いずれ、その経営者のもと、会社が再度経営破綻してしまうのであれば、債権カットをしなかった場合(結果として破産する場合)であっても、債権カットをした場合であっても、いずれにしろ債権の回収はできないのであるから、債権カットを認めることはできません。
法的整理や準則的私的整理手続きにおいては、裁判所や事業再生ADR、地域経済活性化支援機構、中小企業再生支援協議会などの公的な機関が関与する手続きになりますので、会社を破綻させた経営者に対して経営者責任を問うことは必須となります。
たまに、経営者として残ることができますからと言って、法的整理や準則的私的整理手続きの勧誘をしている弁護士を見かけることがありますが、そのようなことは不可能なのです。
かといって、『私的整理』であれば容易というわけでもありませんが、経営者が経営者として残ることがやむを得ないという状況はあると思われます。
弁護士が管理することにより私的整理が可能
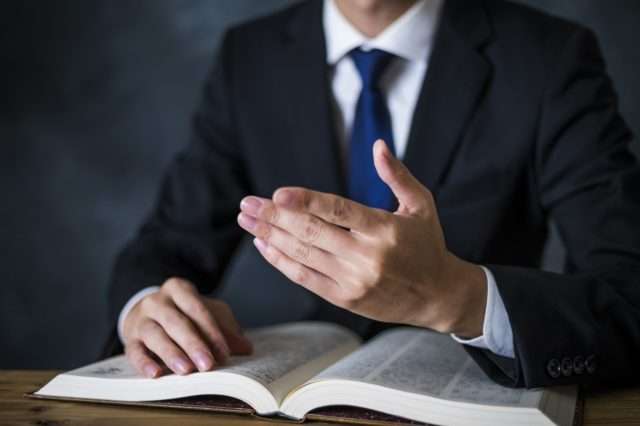 また、弁護士が『私的整理』を主宰して、債権カットを行うことも非常に多く行われています。
また、弁護士が『私的整理』を主宰して、債権カットを行うことも非常に多く行われています。
すなわち、事業再生ADR、地域経済活性化支援機構、中小企業再生支援協議会などが関与しなくても、要するに、銀行などの債権者にとっては、①債務の返済期限の延長(リスケジューリング)や②債務の削減(債務カット)が最もメリットがあるという状況、すなわち、債権カットをしなかった場合(結果として破産する場合)よりも、債権カットをした場合の方が、債権の回収額が大きくなる。
債権カットをすることにより債権の回収額が極大化する状況であれば、銀行などの債権者は債権カットに応じてくれるわけですので、弁護士が『私的整理』を主宰し、会社が、銀行などの債権者にとっては、①債務の返済期限の延長(リスケジューリング)や②債務の削減(債務カット)が最もメリットがあるという状況、すなわち、債権カットをしなかった場合(結果として破産する場合)よりも、債権カットをした場合の方が、債権の回収額が大きくなる。
債権カットをすることにより債権の回収額が極大化される状況であることを説明できれば良いわけです。
会社が、破産せざるを得ない状況というのは、破産しても、銀行などの債権者に対しては1円も配当されない状況と思われ、他方、『私的整理』をすることにより、銀行などの債権者に対して1円でも多く配当することができる状況であるのならば、会社が、銀行などの債権者にとっては、①債務の返済期限の延長(リスケジューリング)や②債務の削減(債務カット)が最もメリットがあるという状況ですので、『私的整理』により債権カットが可能な状況となるのです。
すなわち、完全に破産状態であり二進も三進もいかなくなっている会社であればともかく、そうでない会社、すなわち、破産の一歩又は二歩手前の状態の会社の多くは、このような会社なのではないかと思われます。
必ずしも破産などする必要はない!!
また、完全に破産状態の会社も、必ずしも、破産手続をする必要はありません。
会社が、破産しても、銀行などの債権者に対しては1円も配当されない状況ということは、銀行などの債権者としては、いずれにしろ1円も帰ってこないのであれば、破産してもらっても、破産してもらわなくても、1円も帰ってこないことには変わりがないのです。
問題は、本当に、会社が、1円も配当されない状況であるのかどうか、信用できないというところに問題があります。
ですので、弁護士が管理し、『私的整理』を行い、会社が、本当に、1円も配当できない状況だということが判明するのであれば、銀行などの債権者も、いまさら、特段、そのことをとやかく言うことはありません。
事業の経営というものは、成功することもあれば、失敗することもあり、やむを得ないことなのです。
早めに弁護士へ相談を行う
『私的整理』と法的整理には、どちらもメリット・デメリットがあります。
よって、どちらを選択するのが最善かは、その会社の財務状況や業績などによって異なってきます。
ここで大事なのは、問題を先送りにしないことです。
たとえば、会社の財務諸表を確認すれば、自分の会社が近い将来立ち行かなくなることは目に見えてわかることでしょう。
その状況を放置し、問題を解決するために行動しないようならば、せっかく再建できるものもできなくなってしまいます。
ですので、会社が窮境にあるならば、すぐにでも弁護士へ問い合わせることをおすすめします。
なぜならば、『私的整理』や法的整理のいずれを選択するにしても、法律の専門家である弁護士の知識や、これまでの経験に基づくアドバイスは企業再建のために必要となってくるからです。
いずれにしても、早めに行動していくことが企業再建の可能性を高めることに繋がります。
まとめ
倒産手続きには、『私的整理』と法的整理の分類があります。
会社の状況によっては、柔軟な再建手続きが可能な『私的整理』の方が事業再生を図りやすいケースもあるでしょう。
いざという時の選択肢という意味でも、『私的整理』がどのような手続きなのか、その内容やメリット・デメリットなどは知っておきたいところです。
また、『私的整理』と法的整理のどちらで倒産手続きを取るにしても、できるだけ早く専門家である弁護士へ相談することを検討しましょう。
最も効果的な事業再生計画を弁護士と策定し、会社の建て直しを図っていきたいところです。